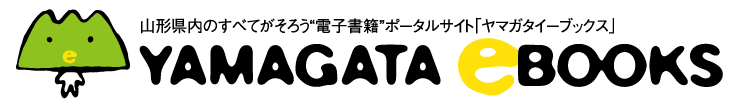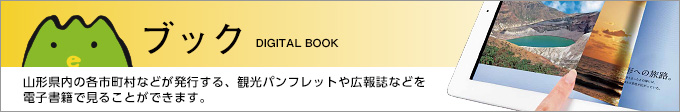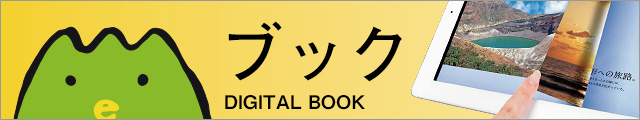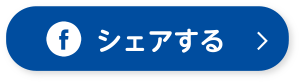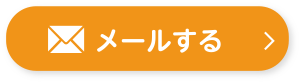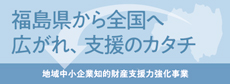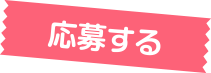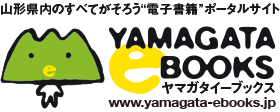- ~ 六十里越街道の歴史と由来 ~
山形県の内陸と庄内を最短距離で結ぶ街道は『六十里越街道』と呼ばれている。かつては内陸から青苧や煙草等を庄内に、また庄内から塩や海産物を内陸に運んでいた。戦乱期には「軍道」として使われたが、この街道を最も多く通行したのは出羽三山参詣者であり、「参詣道」としての役割が大きかった。
出羽三山の登拝口にある別当寺(岩根沢の日月寺、本道寺、大井沢の大日寺)の門前には宿坊等を営む宗教集落が形成され、山先達は夏場には出羽三山を案内し、冬場は各自の旦那湯を巡って御守札を配っていた。さらに街道筋は白装束のお行様で賑わい、山形市の八日町や寒河江市の白岩、西川町の海味、水沢等には宿場町が形成され、多くの宿屋や土産物屋が立ち並び活況を呈していた。
六十里越街道の名前の由来は、六十里の「里」は距離の単位で、昔は6町(1町は109m)を1里としており、この計測によれば、「本道寺~大綱」間の距離がちょうど六十里(約40km)であり、また多くの峠を越えなければならなかったことから『六十里越街道』と呼ばれるようになったと言われている。 -
詳しくはホームページをご覧ください
http://www.gassan-info.com